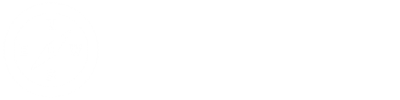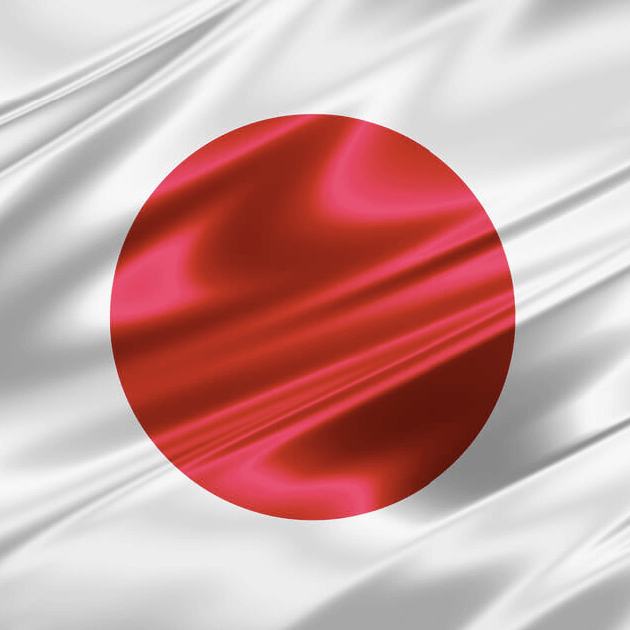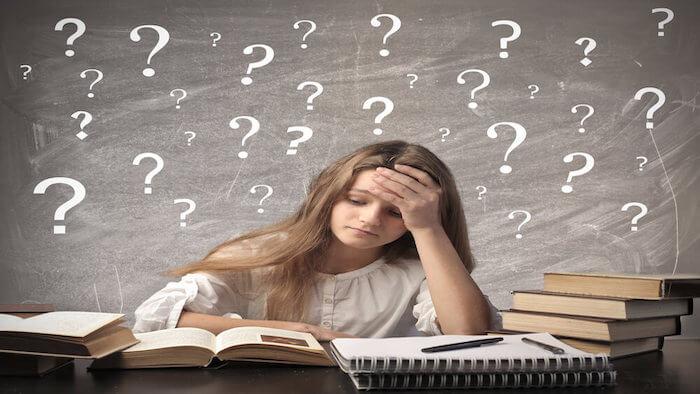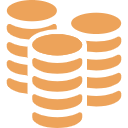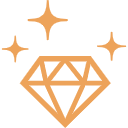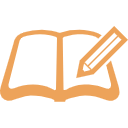「確定申告」ってよく聞くけど、何なんだろう?
このページでは「確定申告って何?」という方に向けて、
- 確定申告とは?
- 青色申告と白色申告の違い
- 確定申告の注意点
こういった知っておくべき確定申告の知識についてお話していきます。
特に自営業の方なら確定申告は避けては通れないものなので、この機会に知識をつけておきましょう。
確定申告とは?

確定申告とは「自分で稼いだお金を国に報告すること」です。
日本の納税制度は申告納税が基本になっていて、毎年1月から12月の1年間分の自分の所得を国に報告することになっています。
サラリーマンのように企業に勤めている方であれば、企業が代わりに国に報告してくれるので自分で申告をする必要はありません。
しかし、自営業のように自分で仕事をしている方は、代わりに申告をしてくれる人がいませんよね。
そこで、国が
自営業とか企業に勤めていない人は、稼いだ金額を確定申告して報告してね!
このように決めたのです。
サラリーマンの方でも、副業で年間20万円を超える所得がある場合は確定申告が必要です。
- 確定申告とは「自分で稼いだお金を国に報告すること」
確定申告はいつ行う?
確定申告の期間は毎年2月15日〜3月15日の1ヶ月間です。
この1ヶ月の間に確定申告を行い、国に1年間分の稼ぎを報告するという流れになります。
時系列にするとこのような感じです。
| 1月〜12月 | 翌年 2月15日〜3月15日 |
翌年 4月〜7月 |
| 稼いだお金を記帳する | 記帳をもとに 確定申告をする |
確定申告をもとに 国が各税金を計算 |
一定の所得があるにも関わらず申告をしなかった場合や、不備があった場合は「加算税」や「延滞税」が課せられます。
- 確定申告の期間は毎年2月15日〜3月15日の1ヶ月間
- 申告をしなかったり不備があれば「加算税」や「延滞税」が課せられる
確定申告はどこで行う?
基本的にあなたが住んでいる地区を管轄している税務署で行います。
事前に届け出を出すことにより、自身の事業所を管轄している税務署で行うことも出来ます。
ただ最近はインターネットで確定申告ができる「e-Tax」が普及してきたので、自宅にいながら確定申告することも可能です。
確定申告期間中の税務署は人で溢れているので、「e-Tax」を使ってネットで行うのをおすすめします。
自分が税務署で確定申告をした時は、行列が出来ていて提出まで3時間近くかかりました…。
- 確定申告は住んでいる地区を管轄している税務署で行う
- 事業所がある地区を管轄している税務署でも可能(届け出が必要)
- e-Taxで自宅からでも可能
確定申告の種類について
確定申告には「白色申告(控除なし)」と「青色申告(控除あり)」という2種類があり、青色申告はさらに「10万円控除」と「65万円控除」に分かれます。
- 白色申告(控除なし)
- 青色申告(10万円控除)
- 青色申告(65万円控除)
「控除」に関してはこちらの記事をどうぞ。
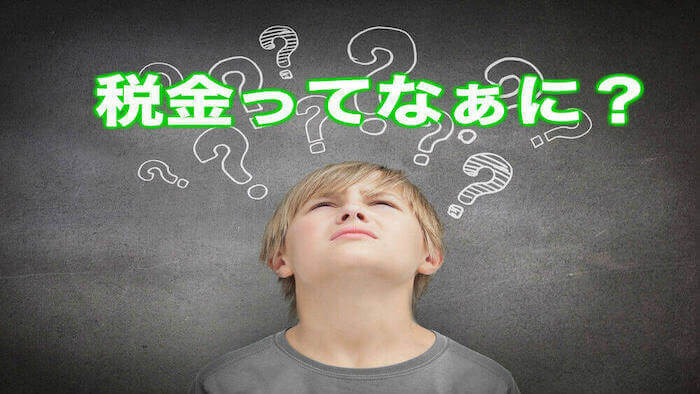
それぞれで控除できる金額が変わってくるのですが、控除できる金額が大きくなるほど「保管しておく帳簿」と「提出する書類」が多くなります。
「帳簿」とは日々の取引内容を記録しておくノートのことで、白色の方は種類が少なくてシンプル、青色の方は種類が多くて少し複雑という感じになっています。
帳簿というと難しいイメージを持ってしまうと思いますが、ようは家計簿です。
それぞれの具体的な違いは下記の通りです。
| 白色申告 | 青色申告 | ||
| 特別控除 | なし | 10万円 | 65万円 |
| 記帳方法 | 単式簿記 | 単式簿記 | 複式簿記 |
| 提出書類 | 収支内訳表 | 損益計算表 | 損益計算表 貸借対照表 |
単式簿記と複式簿記というのは、簡単にいうと
- 単式簿記
→家計簿のような現金の出し入れを記載した帳簿 - 複式簿記
→簿記の資格を持っている人がつけるような難しい帳簿
書類の難易度としては、収支内訳表が最も簡単に作成でき、次いで損益計算表、その次に貸借対照表という感じです。
複式簿記は簿記の知識がないと無理なので、65万円控除を受けようとする方は会計ソフトを使ったほうがいいです、というか必須です。
僕はシンプルで使いやすい「やよいの青色申告オンライン![]() 」を使っているのですが、数字を打ち込んでいくだけで、損益計算表も貸借対照表も作成してくれるので本当に助かっています。
」を使っているのですが、数字を打ち込んでいくだけで、損益計算表も貸借対照表も作成してくれるので本当に助かっています。
セルフプランは1年間無料で使えるので、会計ソフトを使ってみたい方は試してみてください。
それと、「白色申告」と「青色申告(10万円控除)」に関してですが、実はこの2つはやることはそんなに変わりません。
つまり、同じ労力をかけるのだから、白色申告よりも10万円分控除される青色申告の方が断然お得となっています。
また青色申告には後述する特典もあるので、実は白色申告を選ぶメリットってほぼありません。
自営業者の方は、青色申告を選択しないと損をしてしまうので気をつけましょう。
- 確定申告は3種類ある
- 白色申告と青色申告(10万円控除)は、ほぼやることは同じ
- 青色申告(65万円控除)は難しいので会計ソフトを使う
青色申告はどんな特典がある?
青色申告には、10万円や65万円といった控除のほかにも特典があります。
ざっとあげてみると
- 青色専従者控除
- 少額減価償却資産の一括償却措置
- 純損失の繰越制度
ここでは詳しくは触れませんが、とりあえず「こんなにメリットがあるんだ!」と思ってもらえればOKです。
- 青色申告は控除の他にも特典がたくさんある
見落としがちな青色申告の注意点
控除や特典を受けられる青色申告はとてもありがたい制度ですが、注意点があります。
青色申告を行うためには、事前に
- 開業届け
- 所得税の青色申告承認申請書
この2つを税務署に提出しておく必要があります。
申請書は提出する期限が決まっていて、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日までです。
[提出時期]
青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出してください。文章引用元:国税庁
例えば2022年の1年間分を青色申告しようと思ったら、2022年の3月15日までに申請書を提出しておく必要があります。
またその年の1月16日以降に開業した場合は、2ヶ月以内に申請書を提出すればよい、とされています。
申請書は1度提出しておけば、その年度以降も青色申告を選択することができるので、開業届と一緒に早めに税務署に提出しておきましょう。
- 青色申告には「開業届け」と「申請書」の提出が必要
領収書やレシートは大切に保管しておこう
確定申告をするために日々のお金の出し入れなどを記帳しておく訳ですが、その時に必要になってくるのが「領収書」や「レシート」です。
記帳は領収書やレシートをもとに行っていきますし、これらがないと税務調査があった時に購入した物を証明することが出来ません。
そうすると「本来経費として計上出来たものが経費として認められない」なんてことにもなってしまうので、しっかりと保管しておきましょう。
法律でも状況に応じて、数年間は保管するように定められています。
| 白色申告 | 青色申告 | |
| 保管期間 | 5年間 | 7年間 |
ちなみに領収書やレシートの保管方法に決まりはありません。
すぐに帳簿と照らし合わせることが出来ればいいので、ファイルにまとめたり、ノートに張って保管してもOKです。
また領収書の宛名や但し書きは、できるだけ正確に記入してもらうようにしましょう。
- 領収書やレシートは大切に保管しておこう
- 法律でも一定期間は保管するように定められている
【確定申告とは?】青色申告と白色申告の違いや注意点をわかりやすく解説!│まとめ
確定申告の中でも、特に控除ができる「青色申告」は知らないと損をしてしまうので、ぜひ覚えておいてください。
ただ青色申告の65万円控除に関しては、複式簿記などの専門的な知識が必要になってくるので簿記の知識がない方には厳しいと思います。
なので、そういった方は「やよいの青色申告オンライン![]() 」を活用して青色申告をしていきましょう。
」を活用して青色申告をしていきましょう。
確定申告は無視したり、不備があったりすると罰則を受けてしまうので、必ず期間内に正確に行うようにしましょうね。
最低限知っておくべき税金の知識は、下記のページにまとめています。