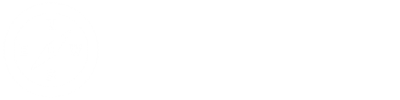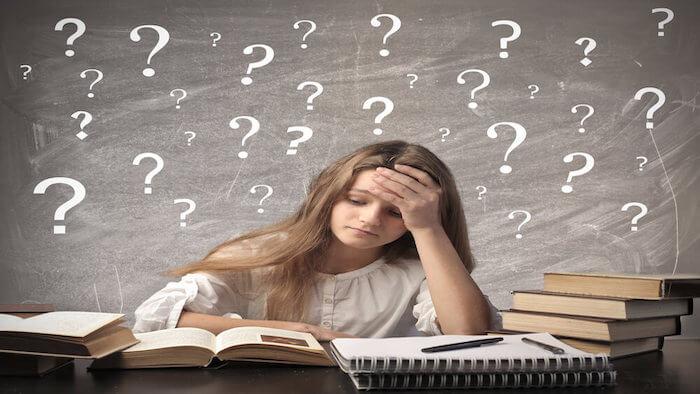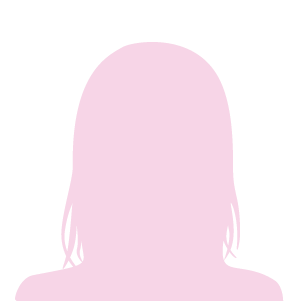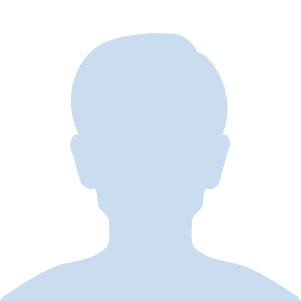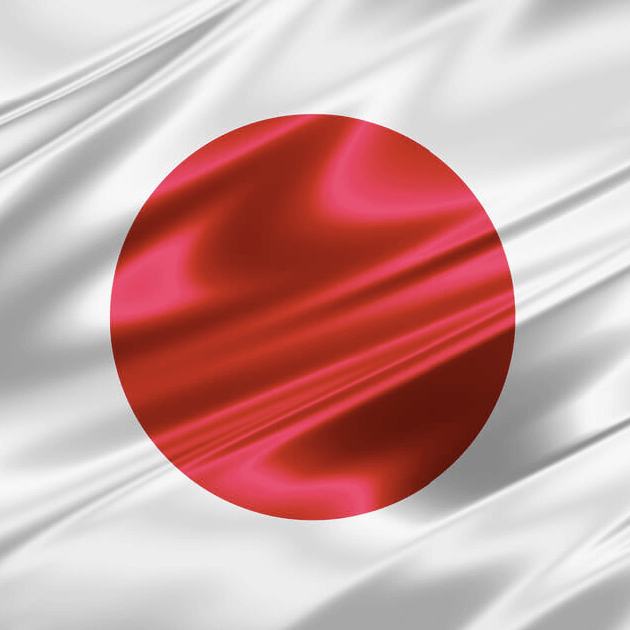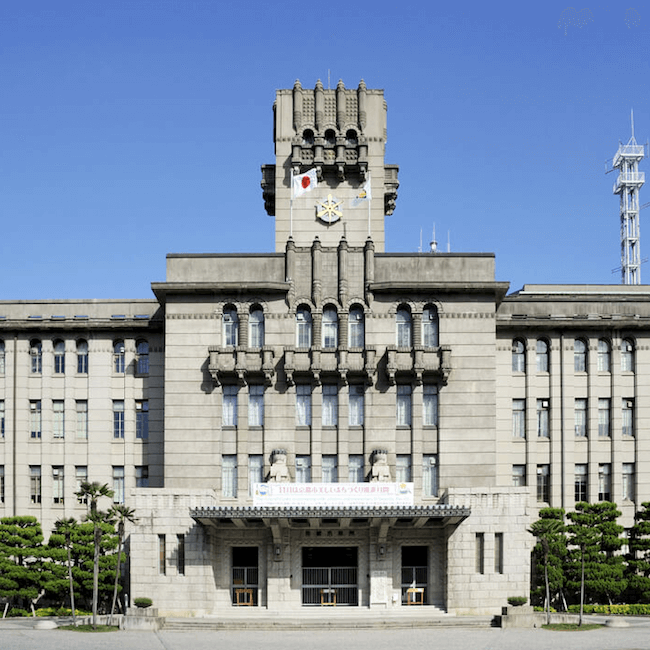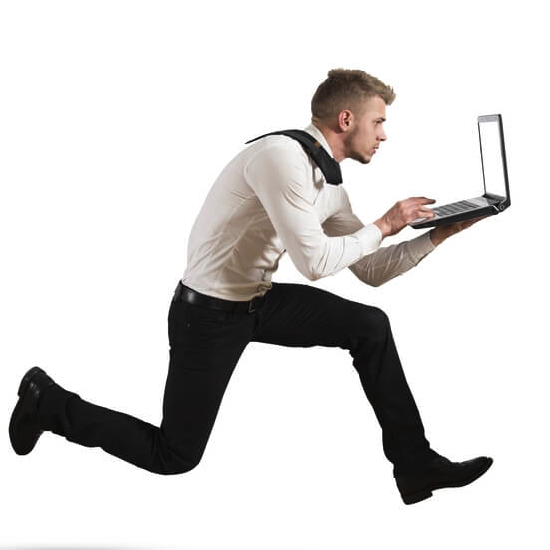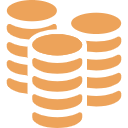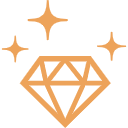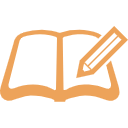「社会保険」ってなんだろう?
私たちが毎月支払っている「社会保険料」。
しかし、お金を支払いながらも「社会保険がどういうものなのか知らない!」という方は意外と多いです。
なので、このページでは「社会保険って何なのかよく分からない」という方に向けて、
- 社会保険って何?
- 社会保険にはどんな種類がある?
- 社会保険の制度は?
こういった事についてわかりやすくお伝えします。
このページを読んでもらえれば、最低限知っておくべき社会保険の知識を身に付けられるはずです。
仕組み自体はまったく難しくないです。
社会保険とは?
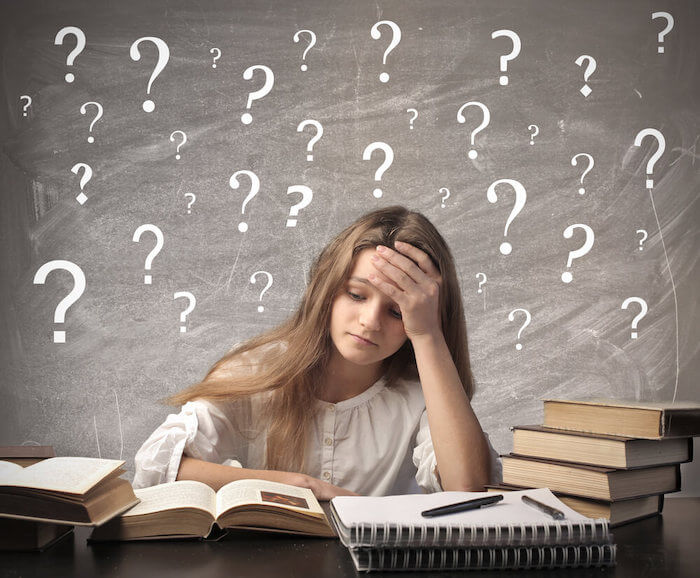
社会保険とは「万が一の時にお金の保障をしてもらえる仕組み」のことです。
例えば、
事故に遭って、入院することになっちゃった…。
デスクがない……そういや俺、昨日クビになったんだった。
このような病気やケガ、高齢化、介護、失業、労働災害などに備えておくものです。
もっと噛み砕いて言うと
将来的に起こるかもしれない様々なリスクに対して、みんなでお金を出して備えておこう!
というものです。
- 社会保険とは「万が一の時にお金の保障をしてもらえる仕組み」のこと
社会保険の種類について

社会保険の種類は様々ですが、身近なものでは下記のようなものがあります。
- 健康保険
- 年金保険
- 介護保険
- 雇用保険
- 労災保険(会社が全額負担)
企業に務めている方であれば、これらの社会保険料が給料から天引きされているはずです。
そして、この中でも特におさえておきたいのが「健康保険」と「年金保険」です。
健康保険は支払っておくことで、病気やケガなどをした時の治療費を安くすることができます。
割合としては基本的に3割負担でよいとされているので、本来10,000円支払うところ、3,000円でよいということになります。
また健康保険では「高額療養費制度」というとても助かる制度を使うこともできます。
高額療養費制度とは?
医療費の自己負担額が高額になった場合に、「自己負担限度額」を超えた分があとで払い戻される制度。
自己負担限度額は年齢と収入水準で決まります。
例えば年齢が70歳未満で、年収500万円の方が、100万円の医療費がかかった場合、3割負担の30万円ではなく約8.7万円の支払いで済みます。
ただし、中には健康保険が適用外の医療もあり、その場合は全額の10割負担になるので注意してください。
一方で年金保険は支払っておくことで、高齢や障害になった時に継続的に国からお金が支給されるというものです。
高齢になったり障害を持って働けなくなってしまったら、お金を稼ぐことが出来ないので、こちらもありがたい制度ですね。
- 社会保険の種類は様々
- その中でも「健康保険」と「年金保険」について知っておこう
健康保険について
健康保険は大きく「健康保険」と「国民健康保険」の2つに分けられます(名称がややこしいです)。
違いとしては、サラリーマンなどの企業に雇われている方が「健康保険」に加入し、それ以外の自営業や無職の方が「国民健康保険」に加入します。
さらに、大きな違いとして健康保険は基本的に企業が半額負担してくれるのに対し、国民健康保険は全額自己負担になります。
またサラリーマンは給料から天引きして企業が納めてくれるので、自分で納める必要はありませんが、自営業の場合は自分で納める必要があります。
| 健康保険 | 国民健康保険 | |
| 加入者 | サラリーマン | 自営業・無職 |
| 支払う 金額 |
企業が半額負担 | 全額自己負担 |
| 支払い 方法 |
企業が 納めてくれる |
自分で納める |
年金保険について
年金保険は大きく分けると「厚生年金」と「国民年金」の2つに分けられます。
こちらも違いとしては、サラリーマンなどの企業に雇われている方が厚生年金に加入し、それ以外の自営業や無職の方が国民年金に加入します。
また健康保険同様、厚生年金は企業が半額負担してくれるのに対し、国民年金は全額自己負担になります。
そして、こちらもサラリーマンは給料から天引きして企業が納めてくれますが、自営業は自分で納める必要があります。
| 厚生年金 | 国民年金 | |
| 加入者 | サラリーマン | 自営業・無職 |
| 支払う 金額 |
企業が半額負担 | 全額自己負担 |
| 支払い 方法 |
企業が 納めてくれる |
自分で納める |
社会保険の制度について

社会保険料は控除として所得から差し引ける
社会保険料の特徴として、支払った分は所得から控除すること(差し引くこと)ができます。
つまり、社会保険料の支払いが大きいほど、支払う所得税を安くすることが出来るということです。
所得税や控除に関しては下記の記事を参考にしてください。
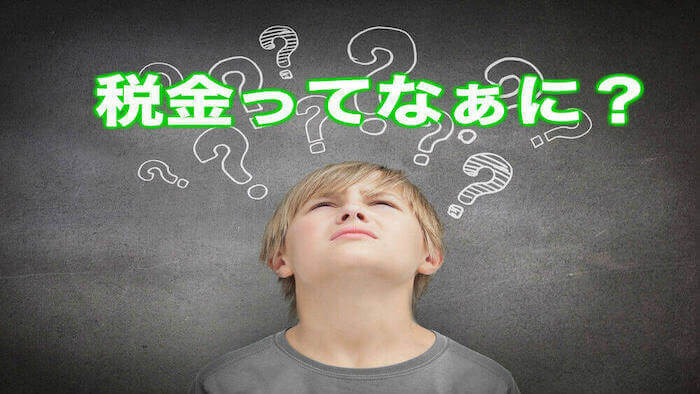
1点だけ注意しておきたいのが、社会保険料を支払った場合、支払った金額は支払った年度の所得から差し引くことが出来るということです。
例えば2021年12月分の国民年金を2022年1月に支払ったとしたら、2022年の控除になります。
2021年12月分の国民年金を…
- 2021年12月に支払う
→2021年の社会保険控除 - 2022年1月に支払う
→2022年の社会保険控除
支払った社会保険料は、支払った年度の所得から控除することになるので、覚えておきましょう。
- 社会保険料は所得から控除できる
- 控除できるのは「支払った年度」
支払いが困難な場合は減免や猶予を受けることが出来る
自営業者が納める「国民健康保険」と「国民年金」の金額に関してですが、それぞれ決定方法が違います。
国民健康保険料は「住んでいる自治体や、前年の所得に応じて決まる」のに対し、国民年金は「一律の金額」となっているのです。
ただ中には独立したばかりで売上が上がらなかったり、事業が軌道に乗らずに毎月の支払いが厳しいという方もいるかと思います。
そういった方を対象に、所得が国の定めた基準より低い場合は、社会保険料の減免(減税と免除)や猶予を受けることができます。
「国民健康保険」に関しては、基本的に自治体が所得から判断して自動的に減税をしてくれるので、申請は不要な場合が多いです。
一方で「国民年金」に関しては、自分で申請する必要があります。
申請して審査に通った場合、
- 全額免除
- 4分の3免除
- 半額免除
- 4分の1免除
- 納付猶予
これらの減免や猶予を受けることができます。
社会保険料を未納のままにしておくと、市役所から督促が来たり保険が適用されなくなってしまうこともあるので注意が必要です。
期限日までにお支払い下さい。
市役所はすごくプレッシャーをかけてきます。
年金の支払いが困難な場合は、近くの年金事務所へ相談に行きましょうね。
さっそく申請だ!
- 「国民健康保険」は基本的に自治体が自動的に減税してくれる
- 「国民年金」は自分で減免申請する必要がある
【社会保険とは?】種類や制度についてわかりやすく解説!│まとめ
ここまでの内容を理解していれば、社会保険についての最低限の知識は身に付いています。
社会保険は万が一の時に役立ってくれる大切なものなので、しっかり納めるようにしましょう。
もし支払うのが難しいようなら、早めに相談して減免制度を活用するようにしてください。
最低限知っておくべき税金の知識は、下記のページにまとめています。