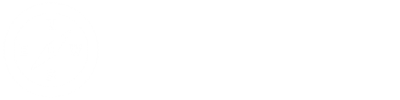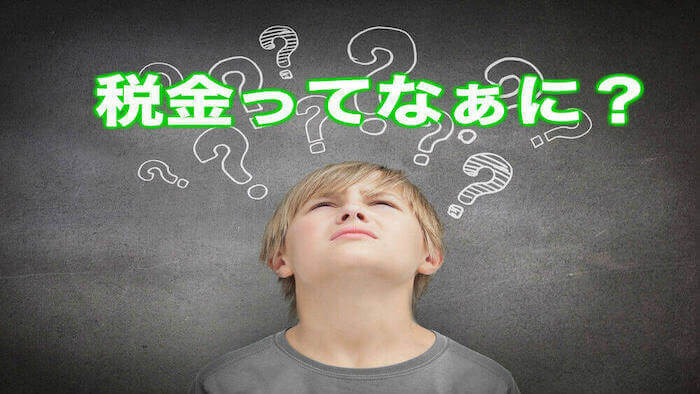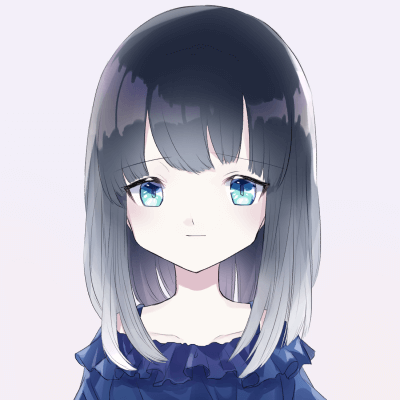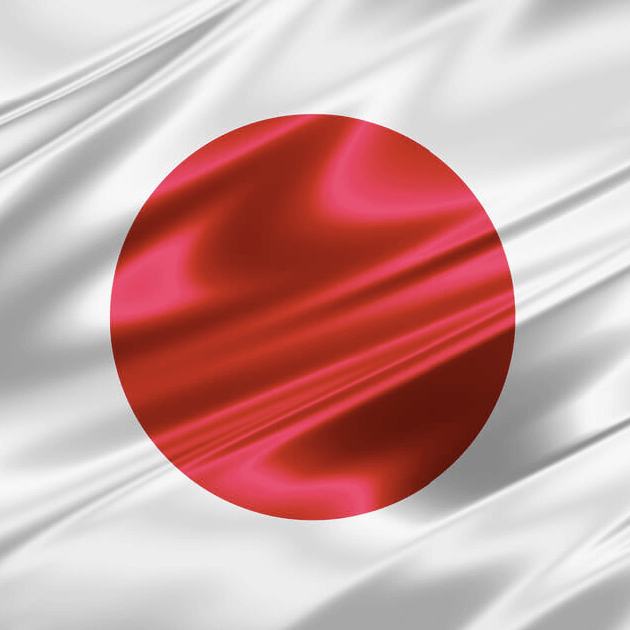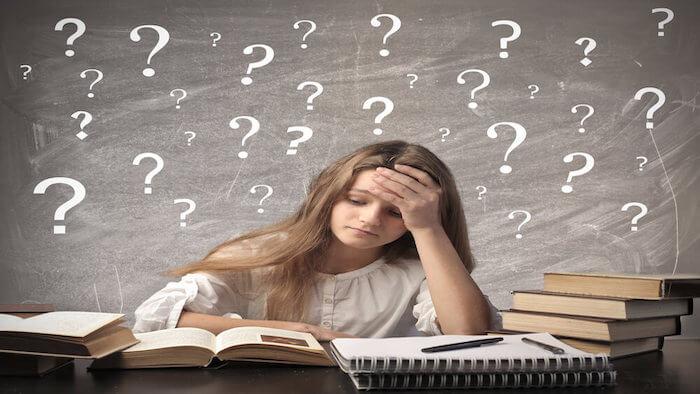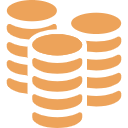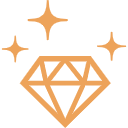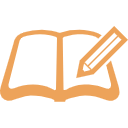税金って難しくて分かりづらいなぁ。
それに興味が持てないし…。
あなたも税金に対して、こういったネガティブなイメージを持っていませんか?
しかし、税金は「知らなかった」というだけで、大きな損失をしてしまうことが多々あります。
実際に僕も知らないことで、税金をかなり多く払っていたことが発覚して、悔しい思いをしたことがありました。
なので、このページでは「税金がわからない」という方に向けて、税金の種類や控除などの基礎について分かりやすく解説していきます。
- 「そもそも税金って何?」
- 「何で税金を納める必要があるの?」
- 「税金を納めなかったらどうなるの?」
こういった疑問はこのページを読んでもらえれば、全て解決できるようになっています。
税金は一生関わっていくものなので、損をしないように上手に付き合っていきましょう。
【税金とは?】税金の種類や控除についてわかりやすく解説!
①「税金」って何?
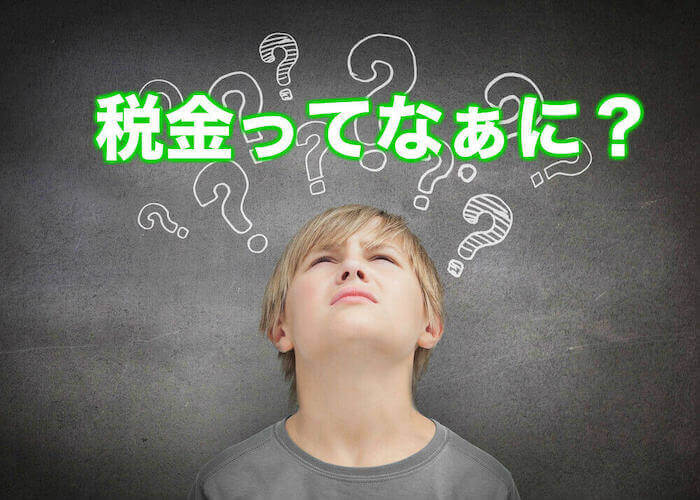
税金を簡単に説明すると、
「日本社会を維持・発展させるためにみんなで出し合ったお金」
のことです。
この社会を運営していくには、どうしても必要になってくるものがあります。
例えば治安を維持するための「警察」や、火災から人々を護る「消防」などですね。
そして、こういったみんなのために働いている人に対して、お金を払わなければいけません。
なので、「社会全体で必要なものに対しては、国民みんなでお金を出し合って支払っていきましょう」と昔に決めたんです。
ちなみに「税金を納めること(納税)」は、「働くこと(勤労)」と「子どもに教育を受けさせること(教育)」と並び、日本国憲法に国民の3大義務として定められています。
つまり、日本国民は「一生懸命働いて、国にお金を払って、自分の子どもに教育を受けさせましょう」ってことです。
- 税金とは「日本社会を維持・発展させるためにみんなで出し合ったお金」
- 税金を納めること(納税)は国民の3大義務のうちの1つ
②「公務員」って何?

税金と切っても切れない関係にあるのが「公務員」です。
公務員というのは「国の仕事を行う人」のことで、先程挙げた警察官や消防士はもちろんのこと、国会議員や市役所の職員などが代表的です。
この人達は国を運営する仕事をしているので、税金からお給料が出されます。
ただ、中にはその税金を自由に使えてしまう人もいるんです。
税金の無駄遣いがニュースになっているのは、そういう人達が自分の利益のために税金を使ってしまい問題になったためです。
それと就職活動などで「公務員は安定」という話題がよく出ることがありますが、公務員は税金からお給料をもらっているので、国が機能している限りお給料が支払われます。
民間企業と比べると、国が潰れる可能性はかなり低いので、安定と言われています。
もちろん移り変わりが激しい現代においては、公務員になれば一概に安定と言える訳ではありませんが、こういった理由で公務員を目指す人も多いです。
- 公務員は「国の仕事を行う人」
- 公務員はサラリーマンより安定している(と言われている)
③税金の種類について

税金には本当にたくさんの種類があるのですが、おそらくもっとも馴染みがあるのが「消費税」だと思います。
お店で商品を購入する際に、必ず商品の代金に加えて消費税が上乗せされますが、消費税はそのお店が後でせっせと国に支払っているんです。
この消費税の税率は年々増えていて、今後もさらに増え続けていくと予想されています。
消費税の他にも
- 働いたら支払う「所得税」
- 生きているだけで支払う「住民税」
- 事業を行ったら支払う「事業税」
- お金を受け取ったら支払う「贈与税」
- お金を相続したら支払う「相続税」
- 資産を持ったら支払う「固定資産税」
- 自動車を買ったら支払う「自動車税」
- お酒を飲んだら支払う「酒税」
- タバコを吸ったら支払う「タバコ税」
- 温泉に入ったら支払う「入湯税」
このような税金があり、僕達の生活は税金で溢れているんです。
- 税金は「消費税」をはじめ様々な種類がある
- 税率は今後さらに上がっていくと予想されている
④「所得税」って何?

「所得税」とは「あなたが稼いだお金に対してかかる税金」で、支払う税金の中で大きな割合を占めています。
また日本では「超過累進課税制度」というものが適用されていて、簡単に言うと
たくさん稼いでいる人ほど、たくさん税金を納めてね!
ということになっています。
つまり所得が多くなれば多くなるほど、支払う所得税も多くなる仕組みなのです。
大きな金額を稼いでいる方の中には不満を抱いている方もいますが、社会の構造上稼いでいる人は少数派になるので、こういった仕組みが機能しています。
- 所得税は「稼いだお金」に対してかかる税金
- 日本は多く稼いでいる人ほど納める所得税が多くなる
⑤「収入」と「所得」の違い
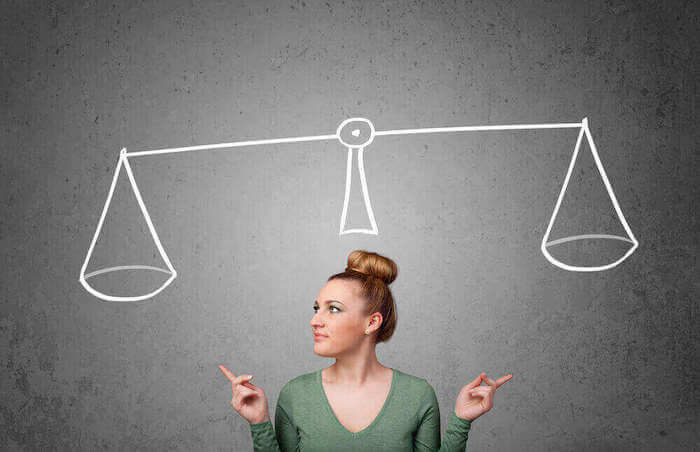
「収入」と「所得」は似ていますが、まったく異なるものです。
まず「収入」についてですが、これは単純に売り上げた金額を指します。
例えば、僕が酒場を経営をしているとします。
いらっしゃい!
この時お客さんに支払ってもらって得た日々の売上、これが収入になります。
しかし、この収入が全て利益として手元に残っているかというと、そういう訳ではありません。
例えば酒場だったら提供する食品や飲料を仕入れる必要がありますし、水道や電気も必要になります。
こういった「収入を得るために使ったお金」のことを「経費」といいます。
そして、収入から経費を差し引いたものが、利益である「所得」となり手元に残ります。
酒場の売上(収入)− 仕入れ代や光熱費(経費)
=手元に残るお金(所得)
- 「収入」は売上そのもの
- 「所得」は収入から経費を差し引いたもの
⑥「控除」って何?

控除というのは「金額を差し引くこと」です。
先程、所得についてお話しましが、所得税はこの所得に定められた税率(5%〜45%)を掛け算して算出されます。
所得×定められた税率(5%〜45%)
=所得税
つまり基準となる所得が少なければ少ないほど、支払う所得税が少なくなる仕組みになっているんです。
なので、いかにして所得の部分の数字を抑えるかが、節税をする上でのポイントになっています。
所得を低くするために収入を低く申告したり、経費を水増しするのは犯罪なので絶対に止めましょう。
ここで役立ってくるのが「控除」です。
控除は所得から規定の金額を差し引けるので、所得を低くすることができます。
(所得−各控除)×定められた税率(5%〜45%)
=所得税
控除の種類は多岐に渡るのですが、
- 無条件で与えられる「基礎控除」
- 子どもがいるのなら「扶養控除」
- 配偶者がいるのなら「配偶者控除」
- 保険料を支払った分だけ引くことができる「社会保険料控除」
こういったものがあります。
つまり控除というものは
他の人の生活を支えたり、保険料を負担してくれているから税金を安くしてあげるね!
という国からのはからいなのです。
このように控除を受けることは、節税における重要なポイントとなっています。
- 控除は「金額を差し引くこと」
- 控除を受けることで税金を安くできる
⑦「給与所得者」と「事業所得者」の違い

世の中でお金を稼ぐ形態は、大きく次の2つに分けることができます。
- 給与所得者
- 事業所得者
1つ目の給与所得者は、「サラリー(給与)」をもらう人のことです。
例えば企業に勤務しているサラリーマンや、パートやアルバイトの方が給与所得者と呼ばれます。
2つ目の事業所得者は、「報酬」をもらう人のことです。
企業に属さず、自分で事業を行っている事業主の方が事業所得者と呼ばれます。
両者を分ける基準としては、「時間給」で働く場合は給与所得者、「出来高制」で働く場合は事業所得者と考えると分かりやすいです。
また申告納税については、給与所得者は企業が「年末調整」をしてくれるのに対し、事業所得者は自分で「確定申告」をしなければなりません。
申告納税とは?
1年間に稼いだ金額を国に報告して、その分の税金を納めることです。
| 給与所得者 | 事業所得者 | |
| もらうもの | 給与 | 報酬 |
| 形態 | 時間給 | 出来高 |
| 申告納税 | 企業が 年末調整を してくれる |
自分で 確定申告する |
ちなみに給与所得者にも経費に当たる「給与所得控除」というものがあり、一定額を収入金額から差し引いてよいことになっています。
ただし、基本的に企業が全て行うので、給与所得者は自分で調整することはできません。
給与所得者でも自分で確定申告をすることは可能で、ケースによっては還付金(税金を支払い過ぎたために戻ってくるお金)が発生したりします。
また一定の金額以上の給与を貰っている場合など、条件によっては確定申告が必要になってくる給与所得者の方もいらっしゃいます。
- 給与所得者は、企業からサラリー(給与)をもらう人
- 事業所得者は、企業に属さず報酬をもらう人
⑧税金を納めないとどうなる?

納税は国民の義務として憲法に定められているので、税金を納めない場合は当然罰則があります。
毎年、税務署の税務官が正しく申告をして税金を納めているか確かめるために「税務調査」というものを行っています。
税務調査を受けるのは稀ですが、受けた場合は帳簿をはじめ通帳や領収証など全て詳しく調べられます。
その結果、自身で修正申告を行ったり、税務署からの処分として更正を受けることもあります。
修正申告や更生があった場合は、「加算税」や「延滞税」が課されます。
「加算税」や「延滞税」の場合は、払うべきだった税金分にプラスして数%程度の支払いになります。
ただし、収入隠しや経費の水増しなどの悪質なものになると「重加算税」を課されたり、場合によっては逮捕になるケースもあります。
また税金にも時効が存在するのですが、時効の期間は個人の状況によって変わるので注意しましょう。
- 未納や不備があった場合には、加算税や延滞税が課される
- 悪質なものになると、重加算税や逮捕されるケースもある
- 税金には時効がある
⑨支払っている税金は社会的信用に繋がる

一般的に自営業はサラリーマンに比べ、社会的信用が低いとされています。
社会では企業に属し毎月給料が支払われるサラリーマンの方が安定している、という風潮なのです。
実際に自営業者の場合、クレジットカードやローンの申請が通らない、なんてことはよくあります。
そこで自営業の場合は、所得税などの税金を支払っていることが、社会的信用を得るための手段になります。
また事故に遭って保障を受ける際など、自身の所得を証明するために所得税を払っておく必要があります。
節税することは大事なのですが、一概に「支払う金額が低ければいい」という訳ではないことは覚えておきましょう。
大切なのはバランスです。
- 自営業は社会的信用が低い
- 支払っている税金が社会的信用に繋がる
【税金とは?】税金の種類や控除についてわかりやすく解説!│まとめ
損をせずに税金と賢く付き合っていくためには、知識を身につけることが必須です。
ただ、税金の本ってどれも難しいし、国のホームページを見ても分かりづらいんですよね。
なので、税金を学ぶ上で特におすすめできる本を1冊だけ選びました。
それが「お金のこと何もわからないままフリーランスになっちゃいましたが税金で損しない方法を教えてください!」です。
僕は今までに税金の本をたくさん読んできましたが、この本がダントツで読みやすかったです。
具体的には
- 表紙のイラストのようにゆる~い感じの雰囲気
- ギャグ漫画なのでスラスラ読める
- 税金の知識0の初心者目線で話が進む
そして「この1冊を読むだけで税金の基礎はOK!」と言えるくらい内容も充実しています。
本当に心からおすすめできる良著だったので、ぜひ読んでみてください。
最低限知っておくべき税金の知識は、下記のページにまとめています。